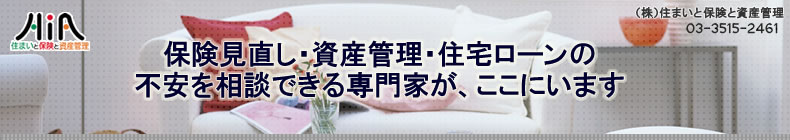
トップページ > ファイナンシャルプランナーによるお役立ち情報 > 自分年金の作り方
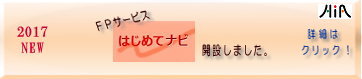 ▼ %83%8c%81%5b%83%56%83%62%83%4e%82%e2%89%ee%8c%ec%82%e0%4f%4b%81%48%88%e3%97%c3%94%ef%8d%54%8f%9c%20%8d%c5%90%56%92%6d%8e%af
取り掛かりは早目が有利、自分年金の作り方
|
| 転ばぬ先の杖 総務省統計局「家計調査年報」(平成20年)によると、夫65歳、妻60歳以上の無職世帯の年平均1ヶ月あたりの実収入は226,043円、実支出は275,430円。つまり、1ヶ月あたり49,388円の支出超過、赤字です。 この数値は、あくまでも全国平均値ですので、実際にはこれまでの収入や住んでいる地域の物価、生活レベルなどによって個人差はあると思います。しかし、日本の高齢者の平均値がこのような実態であることは受け止めなくてはならない事実です。 つまり、老後の資金準備の目安として、1ヶ月あたり5万円の貯蓄取り崩しができるように準備をしておかなければならないということです。当然準備は早い方が楽。老後のことを考えるなんて気が早いよ〜、なんて言っている余裕はありません。早速、準備に取り掛かりましょう。  本当はライフプランを見ないといけないけれど ではいったいいくらを目標に老後生活資金を準備しなければならないのでしょう。 これを知るためには自分のライフプランを確認する必要があります。現在の家族構成、家計の状況、今後のライフイベントなどを考慮したうえで、退職後の生活を具体的にイメージして長期のキャッシュフロー表を作成しないと、本来答えを出すことはできません。 そこで、もっと大雑把に目標額を決める方法をご紹介します。それは、平均値以上にいくらくらいのお金を使った生活をしたいか、というところから逆算する方法です。 上乗せ額は5万円?10万円?15万円? 先ほどの日本の高齢者の平均値を前提にすると、毎月5万円の取り崩しは最低条件です。これにもうちょっと生活の余裕や楽しみを増やしたいと思えば毎月10万円、趣味や旅行など、第二の人生で実現したい夢がたくさんある方は毎月15万円を取り崩すものと考えます。ちょっと乱暴すぎるかもしれませんが、あくまで目安とお考え下さい。 毎月の取り崩し額が決まったら、次は何年分の生活費を準備するかです。平成20年の簡易生命表によると、65歳男性の平均余命は18年、女性は23年です。今後退職年齢が65歳になるとして、夫婦の年齢差を考えると20年をひとつの目安としてみます。すると結果は次のようになります。 【表1】65歳までに準備したい老後生活原資の目安額 取崩額 必要準備額 調整後金額 5万円 × 12ヶ月 × 20年 = 1,200万円 ⇒ 1,087万円 10万円 × 12ヶ月 × 20年 = 2,400万円 ⇒ 2,174万円 15万円 × 12ヶ月 × 20年 = 3,600万円 ⇒ 3,261万円 調整後金額とは、年利回り1.0%で運用しながら取り崩していくものとして、運用益の増加分を差し引いて調整した後の金額です。 よく退職後、余裕を持った暮らしをするためには、退職時に2,000万円から3,000万円くらいの貯蓄を用意しておきたいと言われますが、ほぼ一致するようですね。 さあ、準備額がわかりました。次は具体的にこれらの資金を作る方法です。 資金作りは一時金と積立で 老後生活資金の原資はどこから持ってくるかと言えば、これまでに稼いだお金の中からか、これから稼ぐお金で行う積み立てからしかありません。今の生活もありますから、貯蓄をすべて老後生活資金の原資に回すことはできません。マイカー、旅行、マイホーム、教育費、現役世代も何かと物入りです。いくらなら65歳まで手をつけずに運用できるか、やっぱり長期的なライフプランを考えながらよく考えて決めましょう。 一時金として運用に回す金額が決まったら、それを選択する運用方法の期待利回りに応じて65歳の時点でいくらになると期待できるか計算します。 例えば、現在40歳の人が毎月10万円の取り崩しを目標として、期待利回り3%で一時金300万円を運用する場合、25年後の期待値は627万円です。(【表2】で3%と25年が交差するところの数値 → 209万円 × 300万円 ÷ 100万円 = 627万円) 【表2】一時金で100万円を運用した場合のシミュレーション (前提=1年複利、税引き前) 利回り 0% 1% 3% 5% ───────────────────────────── 10年 100万円 110万円 134万円 162万円 15年 100万円 116万円 155万円 207万円 20年 100万円 122万円 180万円 265万円 25年 100万円 128万円 209万円 338万円 今もっている貯蓄の中から、65歳時点での627万円を確保しました。残る1,547万円は積み立てで準備します。 先ほどと同じく期待利回り3%で考えるとして、【表3】で3%と25年が交差するところの数値は450万円。毎月1万円の積立投資で、65歳時点で450万円を得られます。1,547万円を得るためには、1,547万円 ÷ 450万円 = 34,377円を積み立てる必要があることになります。大体3.5万円ですね。 【表3】毎年12万円(月額1万円)を積立運用する場合のシミュレーション (前提=1年複利、税引き前) 利回り 0% 1% 3% 5% ───────────────────────────── 10年 120万円 126万円 141万円 158万円 15年 180万円 195万円 229万円 271万円 20年 240万円 266万円 332万円 416万円 25年 300万円 342万円 450万円 601万円 読者の皆さんも【表1】【表2】を参考に、(1)いくら上乗せしたいのか、(2)準備期間は何年か、(3)一時金でいくらを準備に回せるのか、(4)想定運用利回りは何%か、を決めて近い数字を計算してみてください。歯を食いしばってでもしなければならない積立額の目安がわかりますので、これを機に家計を見直すきっかけとされるとよいでしょう。 貯蓄の原資作りと、家計の支出削減 先ほどの計算例を見るとわかりますが、想定利回りを高くすればするほど、積立額は少なくて済みます。また、一時金に回すお金を多くすればするほど、やはり積立額は少なくなります。だからと言って、闇雲に高利回りを追求する運用方法をとるのは逆にリスクを高めることになります。 特に65歳というゴールが近い場合には、より慎重でなければなりません。ゴールまでの残り期間に応じて、リターンとリスクの調整を機動的に行い、それでも無理がある場合には家計を見直して、優先順位の低い支出を削減し原資を捻出する努力も併せて行うことが必要です。やっぱりライフプランを作ることと、定期点検を行っていくことが大切だということですね。 最後に伝統的な4資産分散によるインデックス投資の期待利回りをご紹介します。実際には、リスクとリターンのバランス、各資産間の相関性、リスク許容度、ライフプランなどを考慮した上で慎重に決定することが重要です。 【表4】ポートフォリオの一例
※それぞれ期待利回りを、日本債券1%、日本株式6%、海外債券4%、海外株式7%と設定。あくまでも参考値であり。この組み合わせを推奨するものではありません。 株式会社 住まいと保険と資産管理
ファイナンシャルプランナー 山川 正人
|
このお役立ち情報で「
%83%8c%81%5b%83%56%83%62%83%4e%82%e2%89%ee%8c%ec%82%e0%4f%4b%81%48%88%e3%97%c3%94%ef%8d%54%8f%9c%20%8d%c5%90%56%92%6d%8e%af
自分年金の作り方 」についての理解が深まりましたか?※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2009年12月8日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。
|
|
|
|
中立的な専門家として100回を超える紹介をいただきました (詳細はこちら)
住まいと保険と資産管理の「3つの領域に強いFP」が、慎重なあなたを親身にサポートします
| 動画でわかる! FPサービスガイド FP相談サービスに関する案内資料(無料)を請求 ファイナンシャルプランナーの相談サービスに関する「Q&A」 |
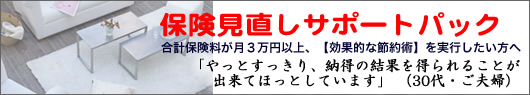
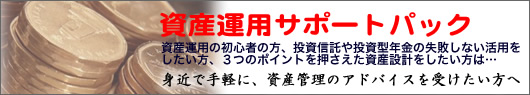
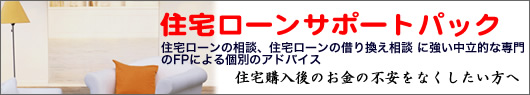
1年以内のマイホーム購入に関する相談をしたい方は ⇒ 住宅購入相談
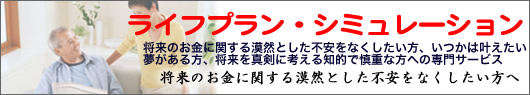
|