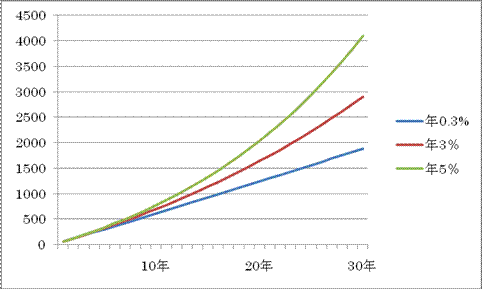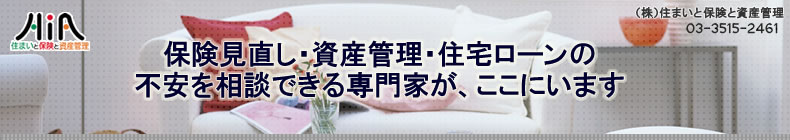
トップページ > ファイナンシャルプランナーによるお役立ち情報 > 自分年金作り
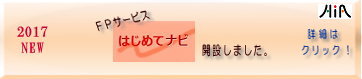 ▼早く始めよう!自分年金作り |
|
退職金と言えば、会社が準備してくれるものと思いがちですが、今は会社が用意した掛け金を、従業員が自分で運用して退職金にするという「確定拠出年金(かくていきょしゅつねんきん)を利用する企業が多くなり、いまや380万人の方が利用しています。自己責任で準備しなくてはなりません。今回は確定拠出年金について、メリットや注意点などもあわせてご紹介させていただきます。 運用方法(運用商品)の選択は加入者個人の判断・自己責任で行い、その運用成果によって将来受け取る金額は変化します。老後の生活が豊かになるのか、それとも切り詰めた生活を強いられるのかが決まってくるから大変です。将来必要な金額が準備できるよう、早くから始めるのが効果的です。 ・買付けタイミングの分散効果 確定拠出年金の特徴である毎月の積み立てが、効果的に働きます。毎月、一定額を積み立てすることにより、基準価格が高い時には少なく、基準価格が安い時には多く買っていくので、取得単価を下げる効果が期待できるという、お馴染みのドルコスト平均法です。 運用を始めて基準価格が下がり続けて数年後に値を戻した場合、一時金で投資していれば、ようやく元本を取り戻した状態ですが、積み立て投資の場合は、その間たくさんの口数を買えているので、元の基準価格に戻したころには収益をあげられます。 ・積立期間中の運用益は非課税 税制上の優遇があり、運用中は利息や分配金などに税金がかからないというメリットがあります。したがって、より多くの資金を運用にまわすことができ、複利効果により大きく増やすことが期待できます。 非課税のメリットを生かすには、利益の出る可能性のある商品を購入すること、つまりリスク商品を活用することです。 高いリターンにはリスク(収益のばらつき)がつきものですから、買付けタイミングの分散の他に、地域分散・銘柄分散も必要です。リスクを軽減することが可能になります。 ・スタートは若いうちから 遅くスタートした人が早くから始めた人に追い付けないのはどうしようもないことです。 25歳から年3%で月5万円60歳まで35年積み立てを続けた場合 投資額合計2100万円 → トータル3707万円 (税金は考慮していません) 45歳から年3%で月12万円60歳まで15年積み立てを続けた場合 投資額合計2160万円 → トータル2723万円 無理に追いつこうとリスクの高い商品に手を出すと、痛い目にあう恐れがあります。 3年間年3%で運用すると → トータルは投資額の約1.1倍に 最初の2年間は年10%増加、最後の1年で20%損失すると → 投資額の約0.97倍に 老後が近い人がリスクの高い商品で運用し最後の時期に損失を出すことのないように気をつけましょう。
・60歳まで引き出せない
確定拠出年金は原則、60歳から年金(または一時金)として受け取れますが、原則、途中引き出しができない仕組みです。退職までの年数が運用期間になりますが、60歳まで10年以上ある人は知らない間に長期運用していることになります。 その期間も、10年よりも20年、30年と長期になればなるほど、その運用効果は顕著に現れます。時間がお金を育ててくれるといわれる通り、利息が利息を生む複利運用が可能になります。
≪積み立て投資の複利運用効果≫(積立金額:月5万円)
・自営業の人や年金制度が導入されていない企業に勤めている人は、個人型年金へ 個人型の対象となるのはこんな人 1、自営業者や農業に従事する人など、国民年金で第1号被保険者に区分される人 ・個人型は所得控除の対象 掛け金全額が所得控除の対象になり、課税所得を抑えられるため、その結果、所得税・住民税の金額が少なくなるというメリットもあります。 個人型は、加入者個人が掛け金を負担しますが、毎月の掛け金の限度額が決められています。 1、自営業者等の拠出限度額は、月額6万8000円(年額81万6000円)。 すでに国民年金基金に加入している場合は、6万8000円から国民年金基金の掛け金を差し引いた額が限度額となります。 2、個人型のサラリーマンの拠出限度額は、月額2万3000円(年額27万6000円)。 ・まとめ 確定拠出年金は将来必要な資金になります。運用期間が10年以上ある若い人は、リスクを取ることを必要以上に怖がらず時間を味方につけて、積極的に学んでいきましょう。 株式会社 住まいと保険と資産管理 ファイナンシャルプランナー 野口正子 |
このお役立ち情報で「自分年金作り」についての理解が深まりましたか?
※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2011年6月14日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。
|
|
|
|
中立的な専門家として100回を超える紹介をいただきました (詳細はこちら)
住まいと保険と資産管理の「3つの領域に強いFP」が、慎重なあなたを親身にサポートします
| 動画でわかる! FPサービスガイド FP相談サービスに関する案内資料(無料)を請求 ファイナンシャルプランナーの相談サービスに関する「Q&A」 |
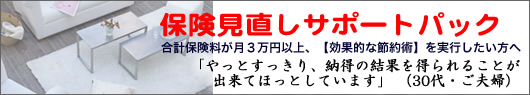
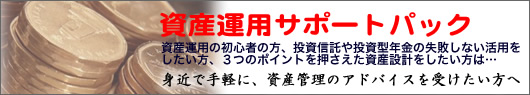
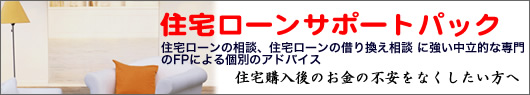
1年以内のマイホーム購入に関する相談をしたい方は ⇒ 住宅購入相談
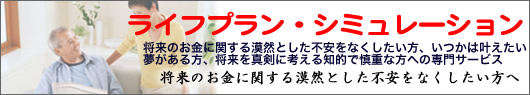
|