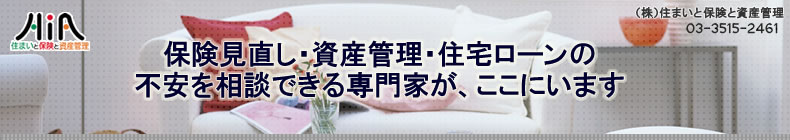
トップページ > ファイナンシャルプランナーによるお役立ち情報 > 長期 分散投資
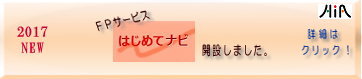 ▼金融危機の中で長期国際分散投資はどのように機能したのか? |
|
資産運用の大原則とされている「長期分散投資」。株式と債券、国内と国外など、値動きの異なる資産に「分散投資」を行い、「長期保有」を続ければ、大きな損失を出すことなく安定した収益を得ることができるとされています。様々に検証が行われ、過去20年〜30年程度の期間でみてその効果が認められていました。 しかし2007年に端を発した国際的な金融危機を経て、「長期分散投資」に対する疑問の声とともに、経済の拡大期には株式への投資比率を高め、後退期には比率を下げるあるいは一旦ゼロにするといった調整をした方がいいのでは、というような声も聞くようになりました。確かに、タイミングよくポートフォリオのバランスを変えることができればリターンは向上します。 そこで、ここ10年程度のパフォーマンスをもとに、ポートフォリオの持ち方によるリターンの違い検証をしてみようと思います。 ●検証の方法 まずは基本となる4資産均等分散(日本株、日本債券、海外株、海外債券に各25%を配分)した場合の運用結果について検証してみます。一般的には広く投資指標として利用されているインデックスを利用するのが望ましく、TOPIX、NOMURA-BPI、S&P500、シティグループ 世界国債インデックスなどが採用されるのですが、無料で簡単に手に入れられない指標もあるため、今回はだれでもできる簡便な方法を取ることにしました。 それは、これら4つの投資指標に連動することを目指すインデックス型投資信託の基準価額を参考にする方法です。今回は、同一社が運用しているインデックスファンド(国内株式・国内債券・海外株式・海外債券それぞれを投資対象とするもの)で代用することにしました。それらのファンドが2001年3月に設定されているため、検証期間は約9年間となりますが、この間景気の山と谷を経ているためそれなりに参考になると判断しました。 ●4つの資産別と4資産均等分散の運用結果 ※各ポートフォリオの説明 4資産分散=日本株式、日本債券、海外株式、海外債券に25%ずつ投資 国内株式・国内債券・海外株式・海外債券は、各資産に100%投資
2001年3月末の基準価額を100とし、2010年3月末の基準価額と比較した場合、日本株式100%、海外株式100%のポートフォリオはマイナスという結果となりました。もっともパフォーマンスがよかったのは海外債券100%で利回りは約4.13%/年です。これに対して、4つの資産に均等分散した場合のリターンは、国内債券のパフォーマンスとそう変わりはなく、利回りは約0.97%/年にとどまりました。
●2つの資産に分散した場合では ※各ポートフォリオの説明 4資産分散=日本株式、日本債券、海外株式、海外債券に25%ずつ投資 国内株・債=日本株式、日本債券に50%ずつ投資 海外株・債=海外株式、海外債券に50%ずつ投資 内外株式=日本株式、海外株式に50%ずつ投資 内外債券=日本債券、海外債券に50%ずつ投資
一見して、この10年間の株式および国内資産のリターンの低迷が見て取れます。債券のみへ分散投資をした場合(内外債券)の利回りが約2.73%/年と一番高く、次いで海外株式・海外債券への分散投資(海外株・債)の利回りが約2.05%/年。それに対して、国内株式・国内債券への分散投資(国内株・債)は約-0.20%/年、株式のみの分散投資(内外株式)は約-1.13%/年とリターンが低迷しています。 海外資産優位、債券優位ということで、バブル崩壊後の日本経済の長期低迷を色濃く反映しているように思えます。
●一定の基準でポートフォリオを変更してみたら・・・ それでは、冒頭で取り上げましたように、一定の法則でポートフォリオを切り替えながら運用するとどれくらいリターンが変わるのか、検証してみました。 ※各ポートフォリオの説明 4資産分散=日本株、日本債券、海外株、海外債券に25%ずつ投資 米金利基準=米国政策金利の上昇下落のタイミングに合わせてポートフォリオを切り替える。 米国政策金利が上昇後にはじめて切り下がるタイミングで、「4資産分散」から 「内外債券」にスイッチ 米国政策金利が低下後にはじめて切り上がるタイミングで、「内外債券」から 「4資産分散」にスイッチ ドル円基準=ドル円為替レートが反転するタイミングでポートフォリオを切り替える。 ドル円為替レートが円安から円高に転換するタイミングで、「4資産分散」から 「日本債券」にスイッチ ドル円為替レートが円高から円安に転換するタイミングで、「日本債券」から 「4資産分散」にスイッチ
米国金利を基準とする場合、スイッチのタイミングは低下を続けてきた政策金利が反転して上昇する時、あるいはその逆に上昇を続けてきた政策金利が反転して低下する時です。検証をした9年間の範囲では、政策金利は短期であげたり下げたりを繰り返すことがないため、金利の上昇あるいは低下に方向が転換すると、その後は数年単位で一方向に進んでいました。スイッチする上でもタイミングを取りやすいと言えます。 それに対して、ドル円レートを基準とする場合は、円高のピークで「4資産分散」のポートフォリオに、円安のピークで「日本債券」のポートフォリオにスイッチしたらどうなるかを検証しました。実際には、現在進行形ではトレンドのピークの判断は難しくあくまで過去のデータを振り返っての検証になりますことをご理解ください。
●結局はリスクコントロール 今回は入手しやすい情報源ということで、過去9年程度のデータを使用しました。長期投資の効果を計るにはやや物足りない期間ですが、とはいえ、4資産均等分散投資を行った場合、今回のような金融危機の中でもプラスリターンを保っていることは評価できるのではないでしょうか。 一方、仮にポートフォリオのスイッチをおこないながら運用した場合、ポートフォリオの株式比率の上限(株式50%)が変わらなくとも、4資産均等分散投資を続ける場合と比べリターンが大きく変わることは、示唆に富むのではないでしょうか。もちろん、今後「米国金利基準」「ドル円基準」の考え方が有効でなくなる可能性はありますし、スイッチのタイミングを間違えれば裏目にでることになりますが、「休むも相場」の格言どおり、時にはポートフォリオ中の株式比率を思い切って調整することもリスクコントロールや運用パフォーマンス向上の面から重要といえるでしょう。
まだまだいろんなパターンが考えられます。今回は紹介しきれませんでしたが、積み立て投資での検証結果も興味深いものがありましたし、3年や5年程度の中短期で試算することもできます。データはマネー情報サイトの投信データなどからとることができますので、みなさんもいろいろなパターンで試してみてはいかがでしょうか。きっとおもしろいと思いますよ。
株式会社 住まいと保険と資産管理 ファイナンシャルプランナー 山川正人 |
このお役立ち情報で「長期国際分散投資」についての理解が深まりましたか?
※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2010年6月16日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。
|
|
|
|
中立的な専門家として100回を超える紹介をいただきました (詳細はこちら)
住まいと保険と資産管理の「3つの領域に強いFP」が、慎重なあなたを親身にサポートします
| 動画でわかる! FPサービスガイド FP相談サービスに関する案内資料(無料)を請求 ファイナンシャルプランナーの相談サービスに関する「Q&A」 |
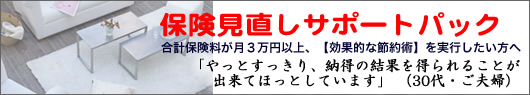
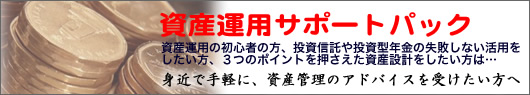
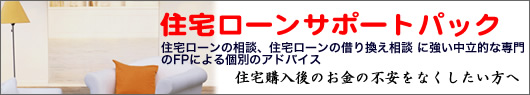
1年以内のマイホーム購入に関する相談をしたい方は ⇒ 住宅購入相談
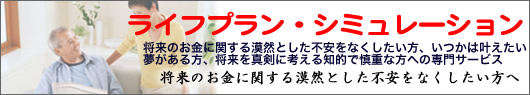
|
