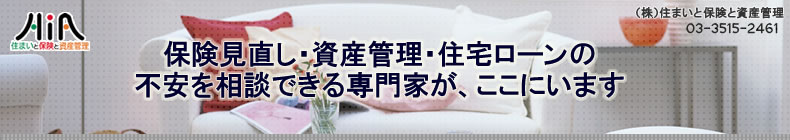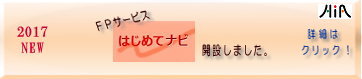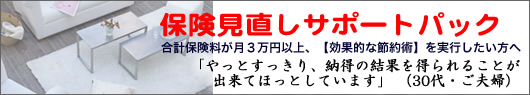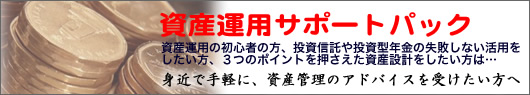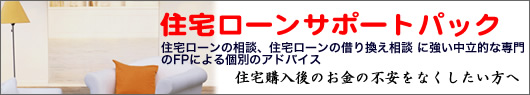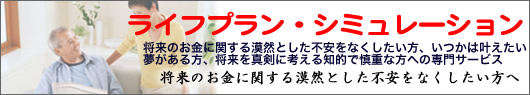毎年夏休みには、小中学生を対象にした金融に関するセミナーが開催されています。
また、大人向けの投資セミナーなどはさまざまな金融機関や組織団体にて年中開催されています。
参加された方から「ためになる話ではあったが、具体的に我が家やわが子にはどう対応したらよいのか。各家庭の家計に対応した取り組み方について悩んでいる」という話を聞いたこともあります。
そこでこの夏休み中に、親子でお金との付き合い方を研究するポイントを3つのステップにまとめてみました。ここでの子どもとは、小学校高学年を中心に中学生までを想定しています。

ステップ1. いつまでも高金利の預貯金商品の復活を待ち望んでいてはいけません⇒「親子でお金との付き合い方の研究」をする親の心構えとして提案です。
日本の金融機関の定期預貯金の金利が4%台、またはそれ以上の水準であったのは、十数年前でしたが、いまだに元本保証のある定期預貯金商品が戻ってくると思っている方がいるようです。しかし、現在のさまざまな状況から考えると、それは近々にはないと私は考えています。
それよりはお金に有意義に働いてもらうためにも、各ご家庭のライフプランに基づいたライフプランシミュレーションをして、各資金を、
1. 生活費など、元本保証のある普通・定期預貯金などで運用する資金。
2. 子どもの教育資金など、短期から中期にかけて運用する資金。
3. 老後の資金など、長期的に運用できる資金。
4. それ以外、中期、長期的に運用する資金。
などの位置付けをして、その家計やライフプランに適合する金融商品(※)での運用を始められることをお勧めいたします。
このことは、親が子どもにお金の付き合い方の研究を導くポイントでもあります。
(※)預貯金も含みますが、株式、債券、投資信託、外貨預金などが該当します。
ステップ2. 子どもに金利(複利)の効果を実感してもらいましょう⇒毎日帳面に記入しましょう
まずは、手持ちの資金(お金)をどんな金融商品で運用するか、その商品の金利の違いによって将来の手取り額が変わってくることを子どもに実感してもらいましょう。
子どもの年齢にもよりますが、一例として、定額のお小遣いを渡していてそのお小遣いの収支を帳面(お小遣い帳)に記帳させているとします。
夏休みの間は、このお小遣い帳に複数の金利を設定して、金利の違いによって利息の増え方を比較するため、帳面の記入欄の枠を増やします。
例:金利1.00%と5.00%の欄を作ります
話を簡素化するために、毎日、子どもに小遣いを100円渡すとします。金利を1日あたり1.00%とした場合、1日目は100円×1.01(1%)=101円(元本:100円、利息1円)。複利計算をすると(複利計算というところもお金が増える重要な要素です)、利息が利息を生み、2日目は(101円(1日目の元本+利息)+100円(2日目の元本))×1.01=203円(元本:200円、利息3円)………(期間中に支出がなければ)………40日目には元利合計が約4,937円になります。なお、利息分937円を実際子どもに支払うのか机上の理論に止めておくかは、各ご家庭にお任せいたします。
金利を5%として運用した場合も作成して、1%の場合と比較してみてください。
もし支出があった場合、例えば3日目に50円を使ったら、203円−50円=153円、(153円+100円(3日目の元本))×1.01=255円(元本:250円、利息5円)と計算を続けてください。
ステップ3. 親子で、金融商品の特徴を知りましょう
ステップ1で、元本確保の預貯金だけでなく、それ以外の金融商品で運用する提案をいたしましたが、各金融商品にはどのような特徴があるのでしょう。それこそ親が「投資セミナー」などでレクチャーを受ける部分かも知れませんが、手間暇を惜しまず、親子でインターネットなどから、「金融商品」や「株式」「債券」などの語句で検索をして、公共機関や金融機関等のホームページ(子供向けサイトもあります)より情報を入手し、親子で理解を深めていただきたいと考えます。
そして、目を付けた業種の異なる株式、債券や投資信託の数銘柄を、夏休みの間、投資運用する必要はありません。実際の値動きのみを追ってみてください。新聞等の論評から、相場全体や個別銘柄が、なぜそのような値動きをするのか理解できるかもしれませんが、ご自分なりの解釈を加え、親子でより各金融商品の理解を深めましょう。
今度の夏休みでは、この癖をつけることができれば十分です。
なぜなら、預貯金しか経験のない親子であっても、もし40日間集中して金融に親しんでいただくことができれば、基本的なところは理解できるからです。
<以降は、参考までに夏休み以降の提案です>
金融商品の理解にある程度の自信を持つことができたなら、夏休み以降に、家計に影響しない位の少額で、預貯金より少しはリスクとリターンが高い複数の金融商品に分散投資をしてみてください。
ここで重要なことは、もしうまく運用ができない場合、その原因を検証して、今後に生かすことです。もし、子どもが理解できる年齢であれば、その結果を共有することが理想的です。一番信頼できる子どもとお金について共通の認識を持つことは、親子にとって将来的にも価値のあることです。
子どもたちにとっては、楽しみの多い夏休みです。
子どもが、将来お金のことを考えることがいやになっては困りますが、考える癖は付けておいてほしいもの。そして、家計という具体的な事例で教えることができるのは親しかいません。
今年の夏休みには、親子で実践的にお金といかに付き合ったらいいか少し考えてみる時間を継続的に作られてみてはいかがでしょうか。
株式会社 住まいと保険と資産管理
ファイナンシャルプランナー CFP 牧野寿和