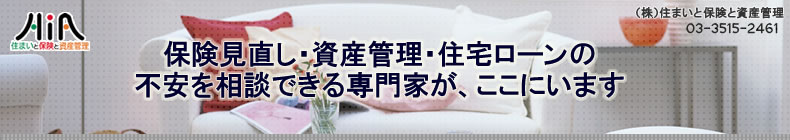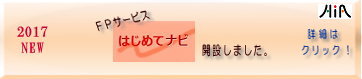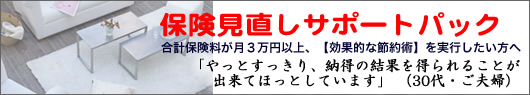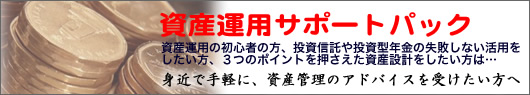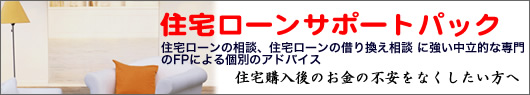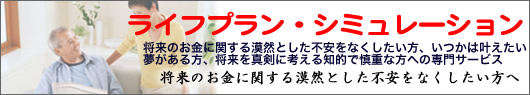近年、BRICS(ブラジル、ロシア、インド、チャイナ)をはじめ、シンガポール、マレーシア、ベトナムなど新興国による経済発展には目を見張るものがある。
2010年、GDPにおいて10.3%の成長を達成し、日本を抜いて世界第2位の経済大国となった中国はもちろん、シンガポールは14.5%、マレーシアにおいても7.2%、ベトナムにおいても6.8%の経済成長を遂げおり、成長率2.8%の米国や1.3%のイギリスなどと比べても大きく水をあけられていることがうかがえる。これら新興国における経済発展はかつての日本における高度経済成長期がそうだったように、国民の所得を引上げ、より豊かな生活を生み出すことになり、世界的経済格差を埋めていくことになるため大変喜ばしいことと言える。しかし、急激な経済発展にはいろいろなリスクが存在することも理解しておかなければならず、その代表的なリスクとしてインフレリスクが考えられる。

2008年のリーマンショック以降、FRBによる超緩和政策により余ったお金は行き場をなくし新興国通貨や原油、穀物などの商品市場へ流れ込むこととなり、その結果、世界的商品市場の急騰をもたらした。それら投機マネーの流入は人々の生活に直結するトウモロコシ、大豆などの食品価格の上昇、ガソリン価格の上昇、砂糖価格の上昇による自動車用燃料エタノールの価格なども大幅に上昇させることとなり、輸送コストの上昇をも招くこととなった。
そこに世界のおける人口の爆発的増加や新興国の所得向上なども手伝い、需給バランスの不均等から物価上昇にさらなる拍車をかける結果となった。国際的な商品相場の急騰は経済発展が遅れている国においてはもちろん、経済発展国においても農村部をはじめとする低賃金層の購買力を減退させ、大きな反発を招くことになる。今年相次いだ中東、北アフリカの反政府運動は物価上昇に対する民衆の不満も理由の一つだといわれている。
また年金生活者や預貯金を取り崩し生活している人などにも直撃することとなる。年金生活者は物価上昇に連動し受給額が増えていく、物価スライド方式が設定されていたとしても前年の物価上昇分が満額で受給額に反映され、物価上昇分増えるということは考えづらい。また、預金生活者は物価が上昇すると取り崩す預貯金に対しての購買力は減少する。商品相場の上昇がもたらすリスクは新興国だけではない。米国においても原油価格が10ドル上昇すると成長率が0.5%押し下げられるとの見方もありFRBによる超緩和政策により、リーマンショック以降、ようやく回復が見えつつある個人消費に冷や水を浴びせる可能性も考えられる。十年来のデフレ基調が続く日本においても、物価は上昇するものの賃金が上昇しないという「悪い物価上昇」が個人を直撃することも考えられる。
経済成長著しい新興国においても最近では高い経済成長率を重視してきた政策から、相次ぎ政策金利を引き上げるなどインフレ対策にシフトしている。また新興国において自国通貨が買われることによる通貨高も、輸入価格を抑えることによるインフレ抑制効果が期待されるため、政府は一部容認しているのではとの見方さえある。各新興国は、かつての日本が経験したようなバブル崩壊を避け、ソフトランディングを成功させることができなければ高所得者はもちろん、中間所得層にまで大きな痛手を与えることになり、日本のように不況から抜け出すために十数年の時間を要することも考えられる。バブル崩壊を避け、経済のソフトランディングとインフレ抑制、各国政府は異なる二つのかじ取りを成功させることを求められている。
退職後、物価の安い海外でのんびりと過すというライフスタイルが数年前にブームになったことがあった。しかしここ数年でそれら新興国の物価は大きく上昇しており、商品物価高は投機マネーの流入や需給バランスから考え、大きく値を戻すことも考えづらい。一方、日本における年金の支給額は物価上昇、物価下落に連動する物価スライド方式を採用しており、2010年の物価は0.7%下落している。これを受け2011年の年金支給額は0.4%引き下げられることが決まっている。‘老後は物価の安い海外で’と希望されている方はこれらも考慮し、しっかりとしたライフプランを作成し、老後生活プランをたてることをお勧めします。
株式会社 住まいと保険と資産管理
ファイナンシャルプランナー 関根 克直