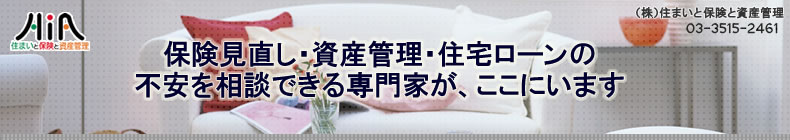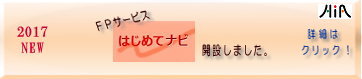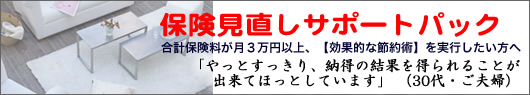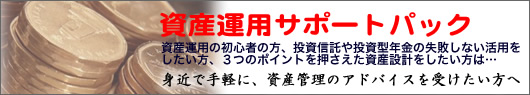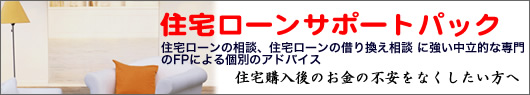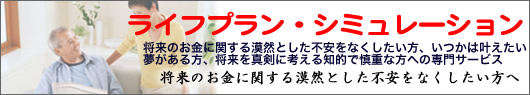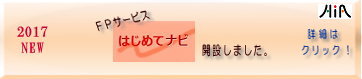
 ▼
▼
%83%8c%81%5b%83%56%83%62%83%4e%82%e2%89%ee%8c%ec%82%e0%4f%4b%81%48%88%e3%97%c3%94%ef%8d%54%8f%9c%20%8d%c5%90%56%92%6d%8e%af
%82%a2%82%dc%82%be%82%a9%82%e7%81%41%95%aa%8e%55%93%8a%8e%91%82%cc%83%81%83%8a%83%62%83%67%82%f0%8c%9f%8f%d8%82%b5%82%e6%82%a4
いまだから、分散投資のメリットを検証しよう
落ち着きを取り戻してきた運用環境
日経平均株価が一時年初来高値を更新するなど、世界的にも落ち着きを取り戻してきた資産運用環境。短い期間で、私たちは世界経済の大混乱を経験したと同時に、資産運用の鉄則と言われる「分散投資」をしていたはずにもかかわらず、運用資産の大幅な目減りも目の当たりにしました。
分散投資は、本当に資産運用に役に立っているのでしょうか?
本コラムでは、分散投資の方法について改めて確認すると同時に、望ましい分散投資をした結果について、実際に投資可能なファンドで運用した場合の検証を試みます。

分散投資の5つの手法とは?
まず、分散投資についておさらいをしておきます。
分散投資はその名のとおり、大事な資産を1箇所にまとめず、あるいは偏ることなく分けて投資をしていくことを指しています。分散投資にはいくつかの手法があります。本コラムでは、5つの分散投資の手法をご紹介いたします。
(1)
銘柄の分散
銘柄を絞って投資した場合、その銘柄が大幅に下落した場合の損失は甚大になります。そこで、「A社に投資するか、B社に投資するか」の選択肢が出てきたときに、「A社も、B社も投資する」という選択肢を実行するのが銘柄の分散です。
(2) 資産クラスの分散
資産クラスの分散とは、お互いに同じ動きをする可能性が低いものに投資することです。一般的に、株式と債券への分散はその代表的な例です。また、金(GOLD)や不動産といった代替資産と呼ばれるものに投資先を広げることも、資産クラスの分散の要点となります。
(3)
地域(通貨)の分散
地域を絞って投資していると、その地域の投資対象が同時にすべて下落してしまう可能性があります。それはよく、為替が円高(海外通貨安)になることで起こってしまう現象です。投資先を複数の地域・通貨に広げることで、それを防ぎます。
以上の分散手法を「対象分散」と呼ぶことにします。いかがでしょう?これは既にご存知のことで、ほとんどの投資家のみなさまは実際に取り組んでいるのではないでしょうか?それにもかかわらず、先般の金融危機の中で、資産の大きな目減りをしてしまったのではないでしょうか?
一方で、以下の2つの分散手法を「時間分散」と呼ぶことにします。どれほどの方が徹底的に実践されていますでしょうか?
(4)
投資期間の分散
投資期間の分散とは、運用を1年で終えるのではなく5年、5年で終えるのではなく10年、というように、運用資産の保有期間を長くすることです。保有期間が長くなるほど、投資結果のバラツキが減ることはよく言われております。「長期投資が大切」という言葉は、まさにこのことを指しています。
(5)
投資タイミングの分散
「資産運用はタイミングがわからないから難しい」ということを耳にします。いいえ、タイミングなんて見なくても良いのです。大切な資金を一度に投資せず、時間をずらして例えば毎月一定額を投資していきます。すると価格が高いときには少なく、低いときには多く投資でき、投資コストと損益のブレを抑える効果が期待できます。ドルコスト平均法とは、この投資タイミングの分散のことです。
分散投資の5つの手法をすべて実行すれば、どんな経済危機でも乗り越えられるのでしょうか?実行しないよりは実行したほうが良いのでしょうか?検証してみます。
個人投資家が投資できるファンドを使って検証してみると
ここでは、実際に個人投資家が購入可能なファンドを用いて、手数料や運用コストを考慮したリアリティの高い検証を試みました。検証に用いたファンドの概要は次のとおりです。
【投資対象】
ファンドA:世界株式の指標に利用される、MSCI-KOKUSAIインデックスに連動することを目指すインデックス型のファンド。資産クラスは「世界株式」と位置づけます。買付手数料は2.1%、信託報酬は0.95%。分配金が出たら無手数料で再投資。
ファンドB:日本株式の指標に利用される、TOPIX(東証株価指数)に連動することを目指すインデックス型のファンド。資産クラスは「日本株式」と位置づけます。買付手数料は1.575%、信託報酬は0.58%。分配金が出たら無手数料で再投資。
ファンドC:世界債券の指標に利用される、シティグループ世界国債インデックスをベンチマークとするファンド。当ファンドは日本債券も投資対象に含まれており、資産クラスとしては「世界債券+日本債券」と位置づけます。買付手数料は1.575%、信託報酬は1.3%。分配金が出たら無手数料で再投資。
【投資期間】
1998年9月末〜2009年8月末の10年間のデータを利用し、毎月末の基準価額で買付を実行する設定としました。
10年間運用した結果は…
|
|
10年後の結果(一時投資)
|
10年間での最大利益率(一時投資)
|
10年間での最大損失率(一時投資)
|
10年後の結果(累積投資)
|
10年間の最大利益率(累積投資)
|
10年間の最大損失率(累積投資)
|
|
A
|
-16.3%
|
+56.1%
|
-39.3%
|
-17.7%
|
+51.7%
|
-41.4%
|
|
B
|
-30.5%
|
+24.2%
|
-46.3%
|
-16.6%
|
+49.9%
|
-36.1%
|
|
C
|
+67.2%
|
+76.0%
|
-9.6%
|
+21.8%
|
+35.1%
|
-5.1%
|
|
4資産合成
|
+6.8%
|
+49.8%
|
-11.7%
|
-4.2%
|
+42.9%
|
-21.5%
|
|
表は、ファンドA・B・Cについて、それぞれ1998年9月末に一時投資して10年間保有した場合と、ファンドA:B:C=1:1:2の割合で一時投資し10年間保有した場合(4次に、投資額に対する最大損益率をみてみます。こちらも、累積投資をした結果の方が、各資産クラスにお産クラスにおける損益のバラツキについては、概ね小さめになったことがわかります。
次に、投資額に対する最大損益率をみてみます。こちらも、累積投資をした結果の方が、各資産クラスにおける損益のバラツキについては、概ね小さめになったことがわかります。
10年の間には、資産クラスによっては5割以上の含み益を得ることもあれば、同じ程度の含み損を抱えることもあります。つまり、投資期間を短く設定してしまうことにより、損失が大きい時点でも運用を終了せざるを得ない可能性があることを示唆しています。ですが、同時に対象分散を図ることにより、最大損失率を抑えることが期待できそうなことがわかります。
万全の体制で資産運用をするには
今回の検証に関しては、5つの分散手法をすべて実行しても、一定の効果はあるものの必ず最後に利益が出るとは限らない、という結果を得ることになりました。ただし、他にもリターンを改善・リスクを軽減する手法はあります。
たとえば、運用コストの削減。今回の検証では、買付手数料は最大2.1%が考慮されており、そのコスト負担は大きいです。ノーロードファンドやETFを活用することにより、長期間にわたり大幅な買付手数料の削減が期待できます。また、資産クラス配分を債券重視の安定型にすることにより、値動きのブレを抑えることも期待できます。そして、資産配分を定期的に元の割合に組み戻すリバランスを定期的に実施することで、適正な資産クラス配分維持と、より効率的な資産運用が期待できます。
株式会社 住まいと保険と資産管理
ファイナンシャルプランナー 渡邊 英利
|
このお役立ち情報で「
%83%8c%81%5b%83%56%83%62%83%4e%82%e2%89%ee%8c%ec%82%e0%4f%4b%81%48%88%e3%97%c3%94%ef%8d%54%8f%9c%20%8d%c5%90%56%92%6d%8e%af
分散投資のメリット検証」についての理解が深まりましたか?
※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2009年9月16日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。
▼3つの領域(住宅購入・保険見直し・資産管理)に強い
ファイナンシャルプランナーの初回相談(3,150円、60分)をご希望の方は
 相談予約専用ダイヤル 0120-374-849 (月〜土 10:00〜18:00) 相談予約専用ダイヤル 0120-374-849 (月〜土 10:00〜18:00)
全国ファイナンシャルプランナー一覧 FP相談予約フォームはこちら
※地域、相談内容、業務多忙等の理由により、担当FPの希望には
お応えできない場合がありますことを、ご了承ください。
|
|
|
|
朝日新聞・読売新聞・日本テレビ・フジテレビなど、様々なメディアにて
中立的な専門家として100回を超える紹介をいただきました (詳細はこちら)
住まいと保険と資産管理の「3つの領域に強いFP」が、慎重なあなたを親身にサポートします
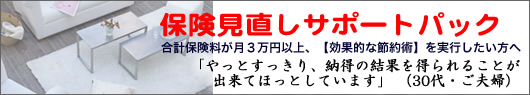
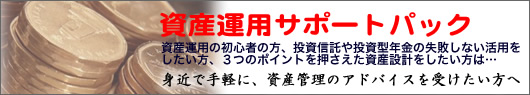
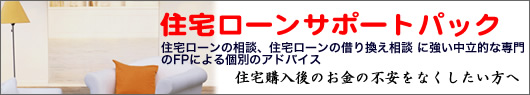
1年以内のマイホーム購入に関する相談をしたい方は ⇒
住宅購入相談
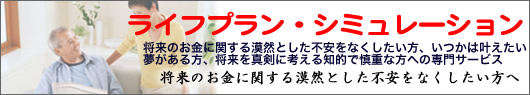
 相談予約専用ダイヤル 0120-374-849(月〜土 10:00〜18:00)
相談予約専用ダイヤル 0120-374-849(月〜土 10:00〜18:00)