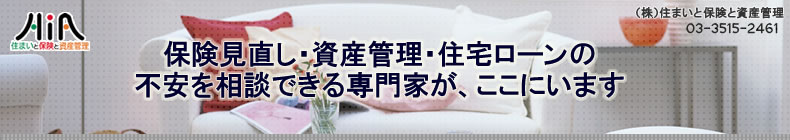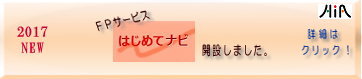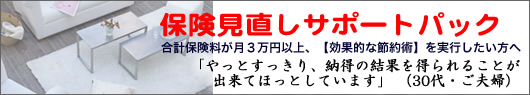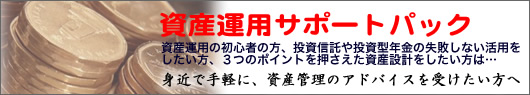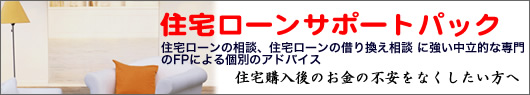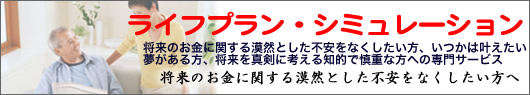�@�T�����[�}���������I�������ɂƂ�A�V��̐����̋��菊�ɂȂ�͍̂�����x�������N���ł��B�Ƃ���ŁA�F����͏����̔N���z���ǂ̂悤�ɎZ�o�����̂��������m�ł����B����́A��Ћ߂����Ă������̔N���z���ǂ̂悤�Ɍ��܂�̂��A�u��{�I�ȍl�����v�����ē����܂��B
�@�@�@�@�@
�P�D�N���́u�Q�̕����v�̑g�ݍ��킹
�@���{�̔N���́A���݁A���炢�n�߂�N��i�K�I��65�˂ֈ����グ���Ă���Œ��ł���A64�˂܂ł�65�ˈȍ~�ł͎��N���̎�ނ��قȂ�܂��B�������Ȃ���A�x������N���͂ǂ�������̂悤�Ɂu�Q�̕����v�ō\������A�Q�̕�����ʁX�Ɍv�Z���������ō��Z���Ďx�����邱�ƂɂȂ�܂��B
|
|
|
60�`64�˂ł��炤�N��
|
65�˂�����炤�N��
|
|
�@
|
��������̋����z���N���z�Ɂg���f���Ȃ��h����
|
���ʎx���̘V������N���́u��z�����v
|
�����N���́u�V���b�N���v
|
|
�A
|
��������̋����z���N���z�Ɂg���f����h����
|
���ʎx���̘V������N���́u��V��ᕔ���v
|
�����N���́u�V������N���v
|
|
�i���j���ʎx���̘V������N���́A���N�����ɂ��x���̗L���A�x���N��قȂ�܂��B
�Q�D�����z���u���f���Ȃ��v�����́u�������ԁv�ŋ��z�����܂�
�@�\���́u�@��������̋����z���N���z�Ɂg���f���Ȃ��h�����v�́A�����N���ɉ��������i�ی��������j���Ԃ̒����ɔ�Ⴕ�ĔN���z�����܂�܂��B��������̋����z�͍l������Ȃ����߁A���������������l���Ⴉ�����l���A�������Ԃ������Ȃ�Ό����Ƃ��ē����x�̔N���z�ɂȂ�܂��B
�@60�`64�˂ł��炤�u���ʎx���̘V������N���́g��z�����h�v�́A
�@�u1,676�~�v�~�u���N�����ɉ��������v�~�u��ی��Ҋ��Ԃ̌����v�~�u0.985�v
�Ƃ����v�Z���ŎZ�o����܂��B���̂����u��ی��Ҋ��Ԃ̌����v���������Ԃɂ�����A���̌v�Z�����u1�����̉����ɂ��A1,676�~����Ƃ����N�����v���Ƃ������Ă���Ƃ������܂��B
�@�܂��A65�˂���́u�����N���̘V���b�N���v�́A
�@�@�@�@�@�@�@792,100�~�~�ی����[�t�ό�����480��
�Ƃ����v�Z���ŎZ�o����܂��i�ی����̖Ə����������Ȃ��ꍇ�j�B480���i40�N�j��������Ɩ��z��792,100�~�����炦��d�g�݂ŁA�������Ԃɂ�����u�ی����[�t�ό����v��480����菭�Ȃ���A���̕��N���z�����Ȃ��Ȃ�܂��B���̂��߁A���̌v�Z�����u1�����̉����ɂ��A1,650�~�i792,100�~��480���j�̔N�����v���Ƃ������Ă���Ƃ������܂��B
�R�D�����z���u���f����v�����́u�����z�v�u�������ԁv�̗����ɔ��
�@�\���́u�A��������̋����z���N���z�Ɂg���f����h�����v�́A�u��������̋����z�v�Ɓu�����N���ւ̉������ԁi�ی����������ԁj�v�̗����ɔ�Ⴕ�ĔN���z�����肳��܂��B��������̋����z�������قǁA�܂��A���x�ւ̉������Ԃ������قǔN���������Ȃ�d�g�݂ł��B�����z�������قǕ��S����ی����������Ȃ邽�߁A��������ɕ������ی����������l�قǔN���������Ȃ�A���S�ɉ������N�����������ƂɂȂ�܂��B
�@60�`64�˂ł��炤�u���ʎx���̘V������N���́g��V��ᕔ���h�v�́A
�@�u���ϕW����V���z�v�~�u���N�����ɉ������旦�v�~�u��ی��Ҋ��Ԃ̌����v
�@�~�u1.031�v�~�u0.985�v
�Ƃ����v�Z���ŎZ�o����i��ی��Ҋ��Ԃ�����15�N3���܂ł̏ꍇ�j�A�u���ϕW����V���z�v����������̋����z�ɂ�����A�u��ی��Ҋ��Ԃ̌����v���������Ԃɂ�����܂��B���̌v�Z�����u��������ɂ�����������̈�芄���̔N�����v���Ƃ������Ă���Ƃ������A65�˂���x������V������N���ɂ��Ă��A���l�̌v�Z�ŎZ�o����镔������ɂȂ�܂��B
�S�D�u�����̉��l�v���ێ����邽�߂̂Q�̎d�g��
�@�N����40�N�߂��̒����ɓn��ی����������鐧�x�ł��B���̂��߁A�������������ƌ��݂ł͋����z�ɑ傫�Ȋi��������A�ȑO�̋����z�����̂܂܌v�Z�Ɏg�p����ƔN���z�����Ȃ��Ȃ�Ƃ����s�����������܂��B�����ŁA�N���z���v�Z����ۂ��u��������̋����z�����̋��������ɒ����v�Ƃ�����Ƃ��s���܂��B���Ƃ��A�u���a36�N4���̋�����10.3�{���Čv�Z����v�Ȃǂ̒������s���邱�ƂɂȂ�A���̂悤�Ȏd�g�݂��u�ĕ]���v�Ƃ����܂��B
�@��������Ɏ����������ׂČ��݂̐����Ɋ��Z����u�ĕ]���v���s���A�ĕ]����̋����z���g�p���āg��������ɂ�����������̕��ϊz�i����ϕW����V���z�Ƃ����܂��j�h���Z�o���܂��B���Z�������������̕��ϊz�ŔN���z���v�Z���邱�Ƃɂ��A�g���݂̋��������h����Ƃ����N���z���Z�o����邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�܂��A�N���z�ɂ͕����̕ϓ����l������܂��B���Ƃ��A�����������Ȃ�ƍ��܂�1���~�Ŕ��������̂�1���~�ł͔����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����܂����A���̎��A�N���z�����܂łƓ����ł���A�N���������I�ɂ͖ڌ�����������ƂɂȂ�܂��B�����ŁA�����̕ϓ��ɉ����ĔN���z�����A�N���z�̎����I�Ȗڌ����x�����߂���}������d�g�����v�Z���̒��ɑg�ݍ��܂�Ă��܂��B�v�Z���ɂ���u0.985�v�u1.031�v�Ƃ������l�������ϓ��ɂ�钲�������ɂ�����A�܂��A�u1,676�~�v�u792,100�~�v�Ƃ����l�������ϓ��������������z�ɂȂ��Ă��܂��B
�T�D�����z���u���f���Ȃ��v�����͒Ꮚ���҂ւ̔z��
�@�u�����z�f�����A�������Ԃ����ɉ����Ďx���������v������̂́A�s�����Ɋ��������������������܂���B�u���Ԋ�Ƃ̕ی����i�ł͂��肦�Ȃ��I�v�Ƃ��������������Ă������ł��B�ł́A�Ȃ����̂悤�Ȏd�g�݂��݂����Ă���̂ł��傤���B
�@�����s�����x�ɂ́u�����Ĕz���v�Ƃ����@�\���D�荞�܂�邱�Ƃ�����܂��B�u�����Ĕz���v�Ƃ́A�������҂���Ꮚ���҂֕x���ړ]������܂ł̏����i�����k�������邽�߂̌o�ϐ���ŁA�Ő���Љ�ۏᐧ�x�̋@�\�̂ЂƂƂ����܂��B�N�����x�ł��u�������Ԃ����ɉ����Ĉ��z���x���������v��݂��邱�Ƃɂ��A�����̍����l����Ⴂ�l�ւ́u�����Ĕz���v���s����A��������̋����̍��قǔN���z�Ɋi�����ł��Ȃ��d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B���̎Љ�ۏᐧ�x�͖��Ԋ�Ƃ̏��i�ɂ͂Ȃ��g����Ȗ�ځh��S���ꍇ������A�Ꮚ���҂ɔz�����������Ĕz���̋@�\������̂����I�N�����x�̓����ł��B
�U�D�܂Ƃ�
�@�ȏ�̂Ƃ���A�N���z�́u�����z�v�Ɓu�������ԁv�����Ƃɗl�X�Ȓ������s���Čv�Z����܂����A���ۂɂ͂���Ɂu���̑��ׂ̍��ȃ��[���v�u��O�v�u�o�ߑ[�u�v�Ȃǂ��l������ĎZ�o����邱�ƂɂȂ�܂��B���̂��߁A�N���z�𐳊m�ɎZ�o�E�����邱�Ƃ͂ƂĂ������ƂɂȂ�܂��B�������A��{�I�ȁu�d�g�݁v��u�l�����v��m���Ă����ƁA����N�������������g�߂Ȃ��̂ɂȂ邩������܂���B
������Ё@�Z�܂��ƕی��Ǝ��Y�Ǘ�
CFP�E������Ɛf�f�m�E�Љ�ی��J���m�@��{��@�M�h