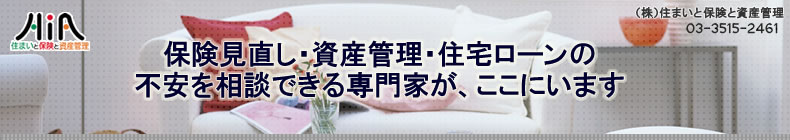
トップページ > ファイナンシャルプランナーによるお役立ち情報 > 年金の増額
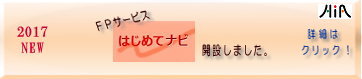 ▼あなたの年金を増額する5つの方法 |
|
あなたは、将来もらうであろう年金に、どのくらい期待をしていますか?
「うちの会社は給料が上がりそうにないので、年金も期待できない」、「国民年金の未納があるから、将来の年金も少ないだろうな」などとあきらめている方が多いかもしれません。ところで、将来の年金額を自らの手で増やす方法があることをご存知でしょうか。今回はさまざまな年金増額術をご紹介します。  1.増額率の高い「繰下げ制度」 はじめに、年金の「繰下げ制度」をご紹介します。繰下げ制度とは、年金の受け取り開始時期を通常よりも遅らせる制度で、もらい始める年齢を遅くするかわりに年金受取額が多くなる仕組みです。年金をすぐもらわない分、利息がつくような制度ともいえ、通常65才からもらう「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」「退職共済年金」で利用できます(老齢厚生年金、退職共済年金では生年月日により扱いが異なることがあります)。 年金をもらい始める年齢は66才から70才の間で自由に決めることができ、もらい始める時期を1ヶ月先延ばしするごとに年金の増額率は0.7%ずつ増えていきます(昭和16年4月2日以降生まれの場合)。たとえば、満額の老齢基礎年金はもらい始める年齢により年金額が次のようにかわります。
受け取り開始時期を通常より5年遅くすると42%増(0.7%×60ヶ月)となり、増額率としては驚異的です。また、増えた年金額を生涯受取り続けることができるのも特徴です。 2.短期的には「繰上げ制度」も増額術に 繰下げ制度とは反対に、通常の年金受け取り開始年齢よりも実際の年金の受け取りを“早める”「繰上げ制度」というものがあります。繰上げ制度は、本来であれば65才からもらう老齢基礎年金を60才から65才になるまでの間にもらい始める仕組みで、通常より早く年金をもらい始める分、1回の受取額は少なくなります(昭和16年4月2日以降生まれの場合、1ヶ月の繰上げにつき0.5%の減額)。ただし、年金の受け取り時期を早めるということは、通常よりも年金を“長い期間”もらうことを意味します。そのため、繰上げてもらい始めてからしばらくの間は、通常の年齢からもらい始めた方よりも、年金の「受取総額(累計額)」では多くなるという現象が起こります。 昭和16年4月2日以降生まれの場合、年金を繰上げてもらい始めてから16年8ヶ月を経過する前までは、65才から年金をもらうよりも「受取総額」が多くなります。たとえば、65才からもらう老齢基礎年金を64才からもらった場合、1回に払われる年金額は6%(0.5%×12ヶ月)少なくなるものの、年金の受取総額は80才8ヶ月(64才+16年8ヶ月)までは通常の年齢から年金をもらう場合よりも多くなります。繰上げてから16年8ヶ月経過した後には、「受取総額」でも通常の年齢からもらった方より少なくなりますが、健康面の問題など、年金を長期間もらうことが難しい特別な事情がある場合には、繰上げ制度の利用が増額術の役目を果たすこともあります。 老齢基礎年金を繰上げた場合の年金額と受取総額
3.国民年金の保険料を余計に払うと また、国民年金の保険料を通常より多く払う「付加保険料」という制度もあります。国民年金の保険料は1ヶ月14,660円ですが、希望すれば月に400円の付加保険料を合わせて払うことができ、将来もらう年金は付加保険料400円の支払いに対し200円増えることになります。 たとえば、付加保険料を10年間払い続けると、48,000円(400円×120ヶ月)の保険料を余計に払い、年金が年額で24,000円(200円×120ヶ月)増えることになります。増える年金額は決して多いとはいえませんが、余分に払った保険料の元が2年で取れる仕組みのため、少しでも年金を増やしたい場合には利用しても良いでしょう。 4.60才以降も国民年金に加入し続けると 65才からもらう老齢基礎年金は、20才〜60才までの40年間保険料を納めて満額がもらえる制度のため、保険料を納めていない期間があると年金額が少なくなります。しかし、60才以降も国民年金に加入し続けて年金を満額に近づけることも可能であり、このような仕組みを「任意加入制度」といいます。60才以降も保険料を支払わなければなりませんが、「どうしても満額の年金が欲しい」という方は検討してみると良いでしょう。 ただし、現在、1年間任意加入した場合、年間の保険料負担が175,920円であるのに対し、年金の増額は年間19,800円であり、任意加入して払った保険料を年金として回収するには約9年かかることになります。老齢基礎年金をもらえるのは原則65才からのため、元が取れるのは74才(65才+9年)頃となります。任意加入制度はこの点も踏まえて利用することが大切です。 5.未納・免除の保険料を事後に払うと 国民年金の保険料を払っていなければ「未納」扱いとなり、将来もらう年金も未納の月数に応じて少なくなります。しかし、「未納」扱いになった保険料は、2年以内であれば後から支払うことが可能です。期限後に払っても「遅延利息」のようなペナルティはつかず、将来の年金額も保険料を期限内に支払った人と区別されることはありません。 また、経済的理由などで国民年金の保険料の「免除制度」を利用している場合、支払いを免除された保険料は10年以内であれば後から払うことが可能です。3年度以上前の保険料を事後に払う場合には、当時の保険料よりも多めの金額を払うことになるものの、通常通りに保険料を支払った人と同等の年金を受け取れるようになるため、「今なら保険料を払える」という場合には検討する価値があります。 生涯にわたり受け取り続けることができる公的年金は、老後生活の大きな支えです。各制度について利用上の注意点も含めて良く検討し、得をする仕組みを賢く使いこなしたいものです。 株式会社 住まいと保険と資産管理
CFP・中小企業診断士・社会保険労務士
大須賀 信敬
|
このお役立ち情報で「年金の増額」についての理解が深まりましたか?
※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2009年4月14日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。
|
|
|
|
中立的な専門家として100回を超える紹介をいただきました (詳細はこちら)
おかげさまで10周年――「3つの領域に強いFP」が、慎重なあなたを親身にサポートします
| 動画でわかる! FPサービスガイド FP相談サービスに関する案内資料(無料)を請求 ファイナンシャルプランナー相談サービスに関する「Q&A」 |
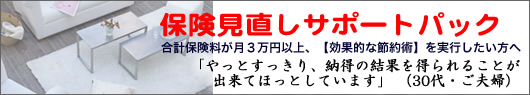
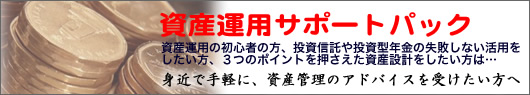
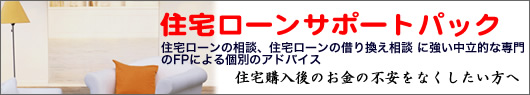
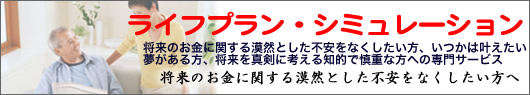
|