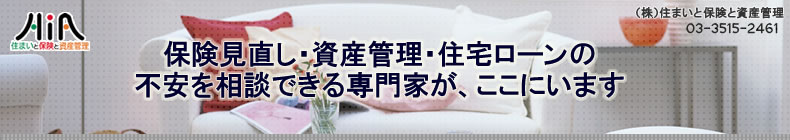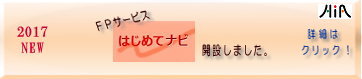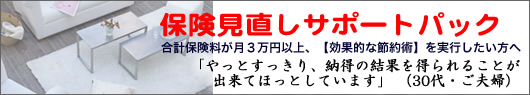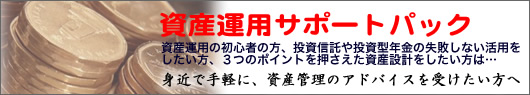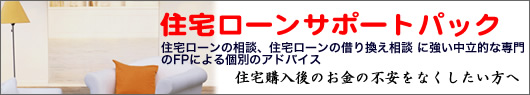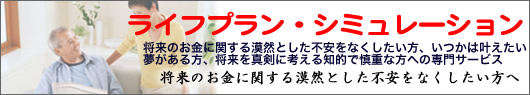セカンドライフ、二つの不安
50代に入ると、そろそろ「定年退職」という言葉がチラチラと頭に思い浮かびます。
「そろそろ老後の資金計画を立てないといけないなあ」と、資産運用の本を買ってみたり、セミナーに参加してみたり、人それぞれの取り組み方はありますが、近頃はファイナンシャルプランナーに相談してみようという方もだいぶ増えてきたように思います。
実際に相談を受けてみると、2つの面でお金に不安を抱えているケースが多いようです。

一つ目は、「老後の生活資金は十分足りているんだろうか?」という不安。
二つ目は、「健康を害したり、介護が必要になったりした時、お金を工面できるだろうか?」という不安です。
仮に、前者を「長生きリスクA」、後者を「長生きリスクB」と呼ぶことにします。
たいていの場合、漠然とした不安を抱えている状態で、具体的な収支を試算してみたり、実際の例を調べてみたりというところまではしていないことが多いです。
そこで、まずは数字に置き換えて、客観的に現状を確認してみましょうと、キャッシュフロー表の作成をお勧めします。
キャッシュフロー表を作成することで、長生きリスクAに対しては資産運用プランの作成、長生きリスクBに対しては保障プラン見直し、と具体的な対策を考えるための手がかりを得ることができます。
二つの長生きリスクへの備え
長生きリスクAに対する備えとして資産運用プランを作成する場合、お金を使途や時期によって3つに分けることが有効といわれます。
たとえば、(1)イザというときに備えるお金、(2)当面の数年間に使うお金、(3)しばらく使わずに運用するお金、というような感じです。
(1)はすぐに引き出せ元本を減らさない預貯金で
(2)は安全性を優先しつつ若干利回りも追及するように定期預金や債権中心の運用、
(3)は長い老後を支える資金を増やすためリスクに十分配慮しながら株式等も組み込んだ運用も検討を、
などと一般に言われます。
これに対して長生きリスクBには、現役時代に必要だった死亡保障を中心とした保障設計から、医療や介護に対する保障へシフトさせることが有力な解決策となります。
単純化すれば、長生きリスクAに対しては資産運用、長生きリスクBに対しては保険、が基本的な対策と言えましょう。
運用商品としての終身介護保険はどうだろう?
介護に対する不安の高まりに応える形で、保険会社各社から終身介護保険が発売されています。
支払い事由の要件や、保険金を一時金で受け取るか年金で受け取るか、支払い上限があるかないかなどは、 当然各保険商品によってそれぞれ違います。
手元で確認ができる2社の商品について、一時払いで保険料を支払った場合の解約返戻金の推移をみてみましたら、A社は9年目に、B社は15年目に返戻率が100%を超えることがわかりました。
返戻率100%とは、別の言い方をすれば投資元本を回復すると言い換えることができます。
また、元本回復後も毎年0.6〜0.9%程度の範囲で、解約返戻金が積みあがっていきます。
将来のことはわかりませんが、 今の金利水準で言えば1年もの定期預金よりは利回りが高いというわけです。
|
A社
|
|
|
B社
|
|
|
60歳男性
|
終身介護年金 40万円
|
介護保険金 500万円
|
|
介護一時金 140万円
|
死亡保険金 500万円
|
|
死亡保険金 500万円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一時払い保険料 →
|
4,468,120
|
|
|
4,438,220
|
|
(単位 円)
|
経過年数 ↓
|
解約返戻金
|
差額
|
返戻率
|
解約返戻金
|
差額
|
返戻率
|
1
|
4,153,900
|
-314,220
|
93.0%
|
3,945,000
|
-493,220
|
88.9%
|
2
|
4,196,600
|
-271,520
|
93.9%
|
3,984,000
|
-454,220
|
89.8%
|
3
|
4,238,900
|
-229,220
|
94.9%
|
4,023,500
|
-414,720
|
90.7%
|
4
|
4,280,900
|
-187,220
|
95.8%
|
4,062,500
|
-375,720
|
91.5%
|
5
|
4,323,400
|
-144,720
|
96.8%
|
4,101,500
|
-336,720
|
92.4%
|
6
|
4,365,500
|
-102,620
|
97.7%
|
4,139,500
|
-298,720
|
93.3%
|
7
|
4,406,800
|
-61,320
|
98.6%
|
4,178,000
|
-260,220
|
94.1%
|
8
|
4,446,400
|
-21,720
|
99.5%
|
4,215,000
|
-223,220
|
95.0%
|
9
|
4,485,100
|
16,980
|
100.4%
|
4,252,000
|
-186,220
|
95.8%
|
10
|
4,524,300
|
56,180
|
101.3%
|
4,288,000
|
-150,220
|
96.6%
|
11
|
4,563,100
|
94,980
|
102.1%
|
4,324,000
|
-114,220
|
97.4%
|
12
|
4,601,500
|
133,380
|
103.0%
|
4,359,000
|
-79,220
|
98.2%
|
13
|
4,639,000
|
170,880
|
103.8%
|
4,393,500
|
-44,720
|
99.0%
|
14
|
4,676,500
|
208,380
|
104.7%
|
4,427,000
|
-11,220
|
99.7%
|
15
|
4,714,400
|
246,280
|
105.5%
|
4,460,500
|
22,280
|
100.5%
|
16
|
4,752,200
|
284,080
|
106.4%
|
4,493,000
|
54,780
|
101.2%
|
17
|
4,789,100
|
320,980
|
107.2%
|
4,525,000
|
86,780
|
102.0%
|
18
|
4,823,800
|
355,680
|
108.0%
|
4,555,000
|
116,780
|
102.6%
|
19
|
4,858,300
|
390,180
|
108.7%
|
4,585,500
|
147,280
|
103.3%
|
20
|
4,887,500
|
419,380
|
109.4%
|
4,614,000
|
175,780
|
104.0%
|
|
「国内債券」資産クラスと考えてみると
これら終身介護保険は変額型ではないため、解約返戻金は基本的に確定利回りということができます。
現在はあいにくと低金利情勢下での契約となりますし、中途換金をしにくいというデメリットもありますが、先ほども申し上げたように定期預金よりはマシな水準です。
もし、退職時に運用可能な資金が数千万円あったなら、長期分散運用を前提としたポートフォリオを組む場合の「国内債権」資産クラスについて、預貯金、国債・社債等に加えて、終身介護保険を組み合わせてみるのもよいかもしれません。
時価ベースで見ると運用効率はよくありませんが、万一介護あるいは死亡という状況になった場合、結果的に受け取る金額を利回り換算すると通常の運用よりもかなり有利になります。
ある意味、要介護状態を基準として利回りが変動するデリバティブです。
解約返戻金の返戻率が100%になるまで10〜15年。
長期分散投資で利回りが平均的な水準に収れんしていく期間にだぶっているように思います。
10年以上運用する資金の一部を充てるなら、中途解約の不利さ、流動性の低さも問題になりません。
運用の成果が終身介護保険の保険料に回されていると考えれば、解約返戻金の増加率が低くても納得できるのではないでしょうか。
60歳以降、セカンドライフを過ごす世代の方々にとっては、利回りの高さよりも介護リスクに対する安心を手に入れることの方が、よほど価値のあることかもしれません。
株式会社 住まいと保険と資産管理
ファイナンシャルプランナー 山川 正人
|